
はちもりたきのふどうそん
八峰町八森字館
最終更新:2025/06/02




- 来来訪:享和元年(1801)11月
- 年齢:48歳
- 書名:雪の道奥雪の出羽路
- 形式:日記、図絵
- 詠歌:ふりつもる雪より雪のおち来かと 滝ついはなみかかるはけしさ
八森に訪れ、瀑布山天滝寺(現在の白滝神社)に詣でて社の由緒を記録する。
「不動堂をたいそう大きく造り、洪鐘に『山本郡八森村別当天滝院』と彫られてある。
堂の左手後方に大滝があり、7尺(約2m)ばかりの剣を二振りm鳥居のように立ててある。
落下する滝の頭には小さな祠があり、不動明王を祀る。
《菅江真澄著・雪の道奥雪の出羽路》

落来る滝の頭に小祠あり、又紫胴の不動あり。
朽木のごときもの立り、これなん、そのむかし円仁の作りたまふをこゝにをさめたりしとぞ。
ふりつもる雪より雪のおち来かと滝ていはなみかゝるはげしさ
《雪の道奥雪の出羽路》
(秋田県立博物館蔵 写本)
2011年11月 八峰町教育委員会
-

あ
- 創建:
- 御祭神:火産霊神、埴山姫神、天照大神、建速須佐之男命、大山積姪子神、羽黒大神
- 例祭日:8月1日
- 特殊神事:
- 御利益:
- 通称:
今より一千百年前、慈覚大師円仁によって開基された。
滝を見て『世に比類なき霊地なり』として滝に打たれ修行し、
自ら刻んだ不動尊白瀑の北方岩土に安置したのが創建と云われている。
中世には当神社周辺は修行の地として修験道が盛んとなり、
藩主佐竹公の崇敬厚く社参され、社領の寄進等があった。
はじめ神仏習合のため不動社と称されたが、明治に至り白瀑神社と改めた。
同43年旧八森村内の三十社が白瀑神社に合祀される。
- 火産霊神(ホムスビノカミ)
- 埴山姫神(ハニヤマヒメカミ)
- 天照大神(アマテラスオオカミ)
- 建速須佐之男命(タケハヤスサノオミコト)
- 大山積姪子神(オオヤマツミノカミ)
- 羽黒大神(ハグロノオオカミ)
- 元旦祭
- 1月上旬:ドント祭、
- 2月1日:厄払い
- 歳祝
- 七五三参り
- 新穀感謝祭
- 除夜祭(大晦日)
- 8月1日:みこしの滝浴び 午後1時~(宵祭:7月31日)

白瀑神社は今より一千百年前、慈覚大師円仁によって開基された。
○中古:
文徳天皇の御代仁寿3年(853)、円仁師回国のみ社に詣で、八森山滝の下清浄にして山色冷澄なるを感じて参詣し、斯かる瀑水は、世に比類なき霊地なりとして滝に打たれ修行自ら刻んだ不動尊白瀑の北方岩土に安置し国土安全を祈願されたのが創建と云われている。
中世には当神社周辺は修行の地として修験道が盛んと成った。藩主佐竹公の崇敬厚く社参され、社領の寄進等があった。
また貞享5年(1688)に、青銅3尺の不動尊を寄進、
「堺の浦より船にのせたてまつり(船主松木、船 勧喜丸)はじめ船出せし日は類船は十隻あまりありけども、みな風にささられ波にあてられ、所々にとどまりぬに、尊像をのせたまうこの船ばかりは、日数十三日にて野代(能代)の浜につかせたまうを見聞く人ことに尊くありがたきことに感嘆しあへり」
それより『波切り不動』とあがめる。」
とあり、水難火難盗賊難みな消散し、一切の所願満足せずということなし、と称賛し信仰された。
近世(1801~1806)には菅江真澄が当社に2度も参り滞在している。
はじめ神仏習合のため不動社と称されたが明治に至り白瀑神社と改め同5年、鄕社に列せられる。
同43年、旧八森村内の30社が白瀑神社に合祀される。
○祭礼:
昔は『六郡祭時記』に4月28日とあってそのにぎわいぶりが記されているが、近年になり8月1日に例大祭が齋行されるようになった。県内はもとより青森県、函館等各方面からも参拝者が見えられる。
現在の社殿(拝殿、長床)は昭和58年に氏子崇敬者の寄進により回収が行われ現在に至っている。
○御祭神:
・火産霊神(ホムスビノカミ)
・埴山姫神(ハニヤマヒメカミ)
・天照大神(アマテラスオオカミ)
・建速須佐之男命(タケハヤスサノオミコト)
・大山積姪子神(オオヤマツミノカミ)
・羽黒大神(ハグロノオオカミ)
○例大祭:
・8月1日(宵祭り 7月31日)…みこしの滝浴び(8月1日午後1時前後)
・主な神事…元旦祭、1月上旬ドント祭、2月1日厄払い、歳祝、七五三参り、新穀感謝祭 除夜祭(大晦日)
○社殿:
・本殿、流造り:面積20,22㎡(6坪)
・拝殿:面積142,15㎡(42,91坪)
・長床:面積93,5㎡(28坪)
○境内末社:
・菅原神社(御祭神 菅原道真公)
・唐松神社(祭神 神功皇后)
・八幡神社(御祭神 本館城主 武田霊神
・太平山神社
・お不動様(滝の北方岩上に安置)
・境内地:面積11,210㎡(約1町2反1畝)
・山林原野:面積20,000㎡(約2町2反3畝)
○みこしの滝あび:
8月1日に行われる白瀑神社例祭当日の渡御祭で、朝7時当番町の男衆たちが白装束で神輿を担ぎ、神社を出発町内を練り歩いたあと、正午過ぎ神社の裏手にある男滝、女滝からなる白瀑(高さ約17m)へ入り、そこでさらに神輿を練って五穀豊穣、海上安全、家内安全、商売繁盛を祈願する。
みこしが滝に入るのは全国でも当神社だけであると言われている。
この渡御祭が『みこしの滝あび』といわれ勇壮な中にも涼気漂う夏の神事として知られる。
滝浴びの起源は戦前といわれている。
戦後、米国のライフ誌に紹介され、国際的にも有名になり全国的に新聞テレビ等で報道されるようになった。
○ドント祭り 1月上旬(第2日曜日)
くじこ青年部によって、毎年正月過ぎに行われるようになった。
境内に設けられた祭場にて家々の古神札や正月のしめ飾り等を夕刻より御祓いのあと、焚きあげを行う神事である。
当日は、氏子青年部による青竹餅、甘酒等の出店もあり、能代山本郡内からの参拝者も多い。
○境内環境
神域としての白瀑神社付近は、樹木や滝があることにより、海岸部より気温が低く普通標高600m付近に自生するブナの木が標高40m付近に自生しており、またモミの木等樹種も多く、植物学的にも貴重でありまた県立自然公園特別区域として環境保全の必要な地域である。
滝のそばや朝の森林には人間の免疫力を高め、細胞を活性化させる力があると云われております。
大神様のご鎮座される神社境内を清浄に保たれるようご協力下さい。
藩主佐竹公は、白瀑神社を崇敬し自ら社参し社領も寄進し、
また貞享5年(1688年)には青銅三尺の不動尊を寄進している。
しかし白瀑神社は、この参道の入口より山の奥にあるため、
道を急ぎ旅する人々は遥か滝の岩の上にある不動像を目に浮かべ手を合わせるようになった。
いつしか道の傍らにも石の不動像が祀られ、波切り不動の遙拝所(ようはいじょ)となった。
不思議なことに、いつの世の大波も、津波もここの所で止まると言い伝えられている。
(『八森町史』より)

藩主佐竹公は、白瀑神社を崇敬し自ら社参し社領も寄進している。
『八森町誌』によると、
「貞享5年(1688)、佐竹公が青銅三尺の不動尊を寄進する。堺より出航するときこれを積みし勧善丸のみ無事にして13日目に着く。
それより『波切りの不動』とあがめる。」
と記されている。
白瀑神社は、この参道の入口より約900m山の手にあるため、道を急ぎ旅する人々は遥か滝の岩の上にある不動像を目に浮かべ手を合わせるようになった。
いつしか道の傍らにも石の不動像が祀られ、波切り不動の遙拝所(ようはいじょ)となった。
不思議なことに、いつの世の大波も、津波もここの所で止まると言い伝えられている。
平成22年3月 八峰町教育委員会
 八杜瀧の不動尊
八杜瀧の不動尊
 八杜瀧の不動尊
八杜瀧の不動尊
| 駐車場 | 案内板 | トイレ |
| 〇 | 〇 | 〇 |
- a
◆参考文献
- 八森町史
- 菅江真澄遊覧記第4巻/菅江真澄 内田武志・宮本常一翻訳
- 国立国会図書館デジタルコレクション
- 真澄紀行/菅江真澄資料センター
- 各種説明板
取材日:2017/07/16
2024/12/15






































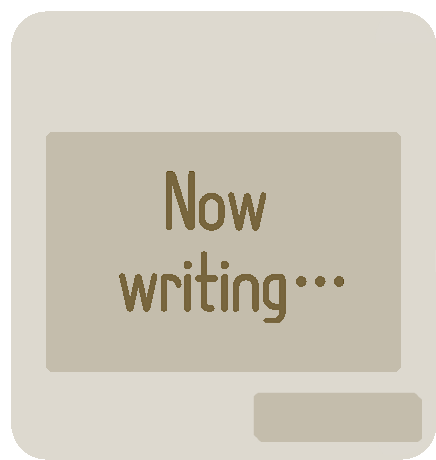

コメントをお書きください