
こまちづか(しゃくやくづか)
湯沢市小野字桐の木田
最終更新:2024/12/09


-



- 来訪:天明5年(1785)4月
- 年齢:32歳
- 書名:粉本稿、小野のふるさと、雪の出羽路 仙北郡
- 形式:日記、図絵
説明文
あたたたたたたた
《あ》
平安時代の歌人、小野小町に想いを寄せた深草少将が小町へ贈った芍薬を植えた場所とされ、『芍薬塚』と呼ばれる。
後に小町堂が建立され、老朽化のため近年現在のお堂に建て替えられた。

花の色は、うつりにけりな いたづらに
わが身世にふる ながめせしまに
(小野小町)
小野小町は大同4年(809)、出羽国福富の荘(湯沢市小野字桐の木田)で生まれました。
幼い頃から美しく13歳の頃、京にのぼりその後20年程宮中に仕えました。
その容姿の美しさや才能の優れていることなど、数多の女官中ならぶ者がいないと言われ、時の帝から寵愛を受けました。
しかし小町は36歳にして、故郷恋しさのあまり生地小野の里に帰り、庵をつくり歌に明け歌に暮しておりました。
京から小野小町が姿を消したので、小町に想いを寄せていた深草少将は急ぎ東へ向かい
長鮮寺跡・桐善寺に仮の住いを求めました。
そして百夜這いの逸話をなぞり九十九日目の夜、降り続いた雨の中森子川にかかった橋とともに帰らぬ人となってしまうのです。
これを聞いた小町は嘆き悲しみ、その亡骸を二ツ森に葬りました。
悲観に暮れた小町は、岩屋堂に住み世を避け香をたきながら一人自像を彫りながら昌泰三年(900年)、
小野小町は92歳で生涯を閉じました。
『小町まつり』は、毎年芍薬の花香る6月第2日曜日に盛大に行われます。
●標柱:菅江真澄来訪弐百周年記念
天明5年(1785)4月14日 菅江真澄 小野のふるさとを訪れる
小野小町遺跡保存会
●説明板:菅江真澄
江戸中期の民俗学者、紀行家。本名、白井秀雄。三河の人。
天明4年(1784)31才出羽へ入国。東北各地を巡遊すること四十年。当時の民間記録を含め、貴重な資料が蒐集されている。
その中の《雪の出羽路》小野のふるさとには、当時の小野村に伝わる小野の小町の
郷土伝承が刻明に描かれている。
文政12年(1829)七月、76才、角館にて死去する。
平成2年 小野小町遺跡保存会

この石土神社(砂利砕石)は、
一、石土彦神(イワツチヒコノカミ)
一、石巣姫神(イワスヒメノカミ)
一、少名彦名命(スクナヒコナノミコト)
の3神を祭り、みなさんの幸せのために建立したもので、この神様を拝み信仰することによってどんな人も幸せになります。
社前の恵比寿様、大黒様のようになることを信じて疑いません。
人間は石器時代の昔より石で鳥や獣を獲り、川で魚を獲って食糧にして来ました。又、石で家や道路を作り大名の城は石で基礎を築き、後世に残る美術作品を生み、近代建築も石と生コンによるところが大きく、婦人のアクセサリーの宝石、さらに人間の死後、墓地も全て石であり、古今人間は石との深いかかわりをもって来ました。
石のもつ不滅の輝きと重厚と壮大さ、大自然の恵みに感謝し、この石土神社を崇拝し、みなさん、幸せになろうではありませんか。
建立者:雄勝町 安藤鴻太郎
📑[コラム1] 小野小町と芍薬
📑[コラム2] 伝説・雨乞い小町
花の色は、うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに
(小野小町)
昭和60年に小野小町遺跡保存会が建立。
小町の和歌が刻まれている。
また堂内には菅江真澄来訪200周年を記念した標柱が建立されている。
小町堂隣、薬局の2階にて営業中。
小野小町の伝説にまつわる資料の他、音声ガイドあり。
店員さん親切な方でした。
アコーディオン

あああ
あ

| 駐車場 | 案内板 | トイレ |
| 〇 | 〇 | 〇 |
小野小町資料館
湯沢市小野小町48-17

- 営業時間 火~木 10:00~15:30
(冬季休業) - 休館日:
- 入館料:
小野小町に関する資料展示、音声ガイド
漢方小町堂2F。
※電話予約制
道の駅 おがち
雄勝郡湯沢市小野橋本90

- 営業時間 9:00~17:00
- レストラン二つ森、各種お食事処、産直、観光案内パネルetc
建物のデザインが市女笠モチーフ。
市女笠はソンブレイロに似ている。メキシカン小野小町。
- 小町まつり
- 小野小町の遺跡
◆参考文献
- 菅江真澄全集/菅江真澄 内田武志
- 菅江真澄遊覧記第1巻・第5巻/菅江真澄 内田武志・宮本常一 訳
- 菅江真澄読本 第1巻/田口昌樹
- 国立国会図書館デジタルコレクション
- 真澄紀行/菅江真澄資料センター
- 小野小町●おののこまち/文=「小町の国」編 絵=金子義償
- 各種説明板
取材日:2017/05/02




























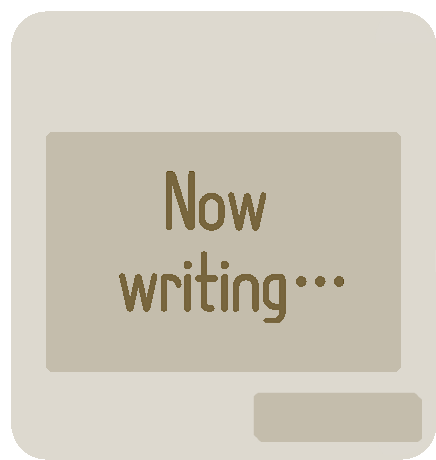
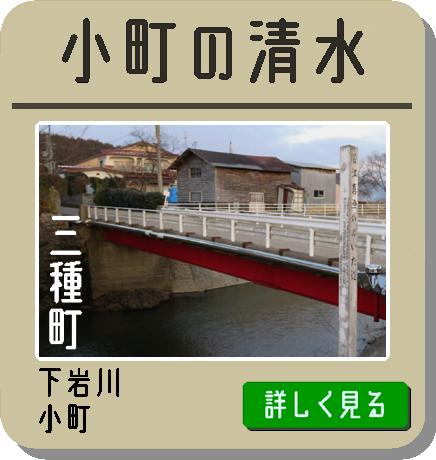


コメントをお書きください