
おおまがりのはなび
大仙市大曲
最終更新:2025/07/17
煙火の祭典


◆全国花火競技大会 概要
- 開催:8月第4土曜日
- 形態:花火競技大会
- 宿泊:大曲 雄物川河川敷公園
Chapter1.昼花火
-
Chapter2.花火競技大会
-
Chapter.
鞠子橋での祭りの風景が描かれており、遠景に打ち上げられた『和火』が描かれている。
《菅江真澄著・月の出羽路 仙北郡》


- 来訪:文政10年(1827)
- 年齢:74歳
- 書名:月の出羽路 仙北郡
- 形式:地誌、図絵
- 来訪:文政10年(1827)
- 年齢:74歳
- 書名:月の出羽路 仙北郡
- 形式:地誌
- 内容:図絵
菅江真澄《月の出羽路 仙北郡》には大曲の眠り流しと題して、鞠子橋での祭りの風景が描かれており、遠景に打ち上げられた『和火』が確認できる。
これが大曲の花火の最古の記録だとされ、若しくは古くより催事に花火が用いられた事の証左とされている。
明治以前から仙北地域、とりわけ大曲周辺は花火職人が集う地域柄で、神社祭典の度に花火を打ち上げて奉納する習わしが根付いていた。
明治43年(1910)、諏訪神社祭典の余興として開催されたのが第1回ろされる。
以降、第二次大戦中やコロナウィルス規制下を除き、雨天時でも毎年開催されている。
◆佐竹義宣国替説
慶長7年(1602)、関ヶ原以後の国替で秋田に来た佐竹義宣一行に
火薬を取り扱う火術師も随伴していたが、雄物川が氾濫し六郷で下船。
火術師は一行から脱落し六郷の娘ろ恋仲に落ち、そのまま六郷の花火師として
根を下ろした説。
◆北前船流通説
火薬に必要な硝石の鉱床は秋田にはないので、
古くから北前船などで雄物川を通じて硝石が流通したのが花火伝来のきっかけ
とされる説。
・昼花火の部
夕方17:35〜18:15
紅、黄、紫などの色煙を駆使して煙竜や煙菊で競技行う。
昼花火を競技にしているのは現在では大曲の花火だけに留まる。
・夜花火の部
夜19:05〜21:30打留
スケジュールに則り各社が順番に種目ごとに花火を打ち上げる。
合間にスポンサー花火、終盤に趣向を凝らした大会提供花火が打つ上げられる。
・10号玉 芯入割物の部
同心円状に真円を描く菊型花火で、4層以上の円の花火が審査対象となる。
・10号玉 自由玉の部
芯入割物と重複しない型の花火を対象とする。
創造性と技術的なまとまが求められる。
・創造花火の部
昭和39年(1964)の第38回から競技種目に加えられた。
割物・ポカ物問わず各自テーマに沿って自由にイメージ表現する。
BGMに合わせて打ち上げるタイミングや花火の色彩構成など見るべき所は多い。
流行に則したものや、テーマ重視のものなど、花火会社の創造性が問われる。
・大会提供花火
競技花火とは異なるデモンストレーション。
協同組合青年部がテーマやイメージを音楽と花火で表現したもので打ち上げは5分以上にも及ぶ。
会場の幅900mを全て使うワイドスターマインを皮切りに総数約2000発以上もの花火が上がる。
・ペンライトセレモニー
全発打ち上げ終了後、観客が感謝の意味を込めて懐中電灯やペンライトを振るう。
それに応えて花火師達が誘導灯を振って合い通ずる光景はもは例年の恒例の風景となっている。
| 駐車場 | 案内板 | トイレ |
|
〇 (ほぼ有料) |
〇 | 〇 |
花火伝統文化継承資料館 はなび・アム
大仙市大曲大町7-19

- 開閉時間 9:00~17:00
- 休館日 毎週月曜日
- 入館料 無料
- a
◆参考書籍・施設
- 花火伝統文化継承資料館『はなび・アム』
- 大曲の花火 公式プログラム
- さきがけ新書 大曲の花火 100年の記録/秋田魁新報社
- 国立国会図書館デジタルコレクション
- 秋田の祭り・行事/秋田県教育委員会編
取材日:ほぼ毎年




















































































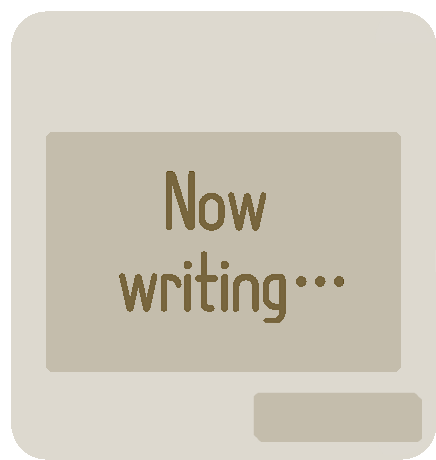


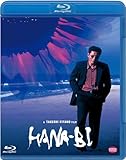
コメントをお書きください