
がんにんおどり
南秋田郡八郎潟町
最終更新:2025/06/25
ニャンパチかわいい


- 祭日:5月5日
- 形態:奉納踊、山車、寸劇
- 巡行:八郎潟町一日市区内
- 人員:約12人(音頭あげ1、踊り手4~5、唄い手3~4、寸劇2)他巡行者多数人
- 奉納社:一日市神社
街中に衣装を着た子供を乗せた山車が回り、一日市神社へ奉納したのちに
八郎潟町駅前の広場でショー的に演目が開かれる。
Chapter1.由緒
- 正徳4年(1714)、
高岡山に副川神社が再興されてから間もなく、
真坂、夜叉袋、一日市の3集落で踊っていた奉納踊りを
神社の祭典プログラムに加えたもの。 - 願人とは?
伊勢・熊野信仰の芸人となり、地方をドサ回りして宗教を広めた人たちを指す。
- 江戸中期(天明頃)、
羽立の村井某が伊勢参宮をして、全国的に人気だった伊勢踊りのスタイルを
従来の願人踊りに取り入れた。 -
- 明治元年(1868)、
歌舞伎の仮手本忠臣蔵(五段目)のユーモラスな寸劇を取り入れる。 -
- 戦時中は一時途絶えたが、昭和33年(1958)に地元の芸能研究会が保存に乗り出した。
以降、開催は5月5日で固定される。
Chapter2.演舞
-
音頭上げ(1人)
黄色のタスキをかけ、幣足・大鈴をつけた豊作礼を持ち先頭に立つ。 -
-
踊り手(4人)
女の長襦袢を羽織り、頬かむりをする。 -
-
唄い手(4人)
踊り手と同じく女の襦袢、傘の頭に幣束を立て、この中に入り並列する。小鈴を鳴らす。 -
-
与一兵衛と定九郎(各1人)
寸劇手。
-
ボーボコ節
町内を一巡して神社に参内する行進曲。数え唄。 -
-
桃太郎さん
桃太郎の粗筋を唄う。ストーリーは似るが、こちらは桃でなく瓢箪となっている。 -
歌舞伎の演目をモチーフに明治に入ってから追加された寸劇。
与一兵衛と盗賊・ 定九郎のユーモラスな騙し合いが展開される。
自分の娘を身売りに出して得た大切な金を懐に抱え、帰路につく与一兵衛。
「どーれ、松の木の下で一服つけようかァ。」
そこで山賊の定九郎が金を巻き上げようと迫る。
「この物騒な夜道を一人旅とは大胆!ワシと一緒に道連れになって行こうか、行こうか」
「わ、わしゃァ年寄りのことなれば、あとからブラブラ参ります」
「そなたの懐に金なれば、四・五十両の金、縞の財布に入ってるのを話者見込んできた」
「いつの間に見たべや!この泥棒ケシ!」
あの手この手で定九郎は仕掛けるが、与一兵衛も負けじと応戦するのだった。
「なもはねゃ、なもはねゃ」
「くたばれ!くたばれ!」
編集中
編集中
編集中
編集中
INFORMATION
| 駐車場 | 案内板 | トイレ |
| 〇 | 〇 | 〇 |
- 大川
- 大川一日市神社
◆参考文献
- 八郎潟町史
- 各種説明板
取材日:2018/05/05





















































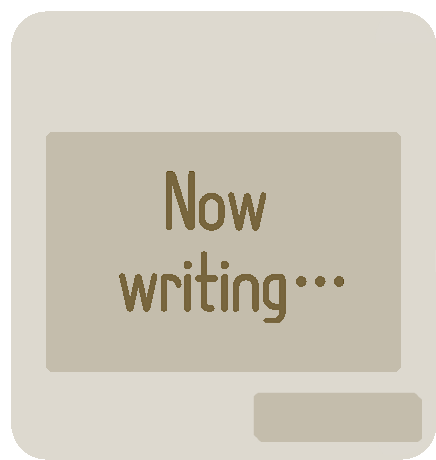



コメントをお書きください