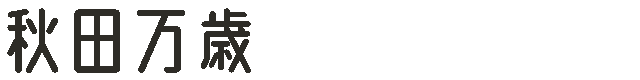
【あきたまんざい】
【芸能】

新年、笑い初め
『万歳(萬歳)』は年初に家々を訪問し祝言、門付けして歩く祝福芸能の一つ。
『太夫』と『才蔵』と呼ばれるの二人一組の秋田弁の掛け合いでさながら漫才もかくやの調子で演じられる。
最盛期の明治後期には秋田市内でも15組の万歳師組合があった。
昭和49年(1974)、秋田県の無形文化財に指定された。
かつては正月の風物詩の一つであり昭和40年代頃までは秋田市内でも巡行が行われていたそうだが、現在は保存会による公演が不定期に行われるに留まる。

袴に松竹鶴が背中に大きく染め抜かれた上衣を羽織り、頭に侍烏帽子をつける。扇をひろげて立つ。
袴に頭巾、鼓を持ち、囃子舞によって面も使う。鼓を持ち囃す。
太夫と才蔵の二人一組の掛け合いによって演じられ、12段の儀式万歳から始まり、秋田弁で語る噺万歳へとつながる。
儀式万歳は家を新築した時に演じる「家建」や久保田城下の名所・繁盛をうたう「御国」、表6段、裏6段からなる。
噺万歳には男鹿島めぐりなど14種があり、ほかに踊りと歌がつく官能的な『コッカラ舞』『秋田音頭』『えびす舞』『つっつき舞』などの噺舞もある。
近年ではカタにとらわれない時事ネタ風刺や新ネタなども囃され、聞いてて楽しい。
江戸時代後期、秋田藩の生活習慣や風俗を説明した調査報告書「秋田風俗問状答」には秋田万歳についての説明と図絵が添えられている。
万歳はもともとは三河の国より常陸へ来り往てけるが、慶長年間にこの地へ移って来たものだという。
古い記録などがありそうである。
《秋田風俗問状答》
この記録にもあるように、ルーツは三河万歳の系統と言われていましたが、近年の比較研究では尾張系の万歳の流れをくむ江戸方万歳ではないかとする説が有力視されている(秋田市民俗芸能伝承館 ねぶり流し館の展示より)。
私歳の上祖も三河国より常陸国に来りて、その家、今、秋田ノ久保田に在りて代々針生代々夫といふ一派なり。
烏帽子に松竹鶴亀の紋(カタ)ある水干を着て、才蔵は広袖原綿入を着て浅黄のちょっへい頭中によそいたちぬ。古来より家に伝ふ十二段の曲あり、[中略]世々長々子々孫々と伝へうつりて三ふりとは大にことなれり。けれどしかすかにむかしは残りたる。
《菅江真澄著・筆のまにまに》
INFORMATION
【関連施設】
◆参考文献・施設
- 菅江真澄遊覧記第5巻/菅江真澄 内田武志・宮本常一翻訳
- 菅江真澄随筆集/内田武志 編
- 秋田風俗問状答/金森正也 翻刻・現代語訳・解説
- 国立国会図書館デジタルコレクション
-
- 秋田叢書
- 秋田風俗問状答
- 秋田民俗芸能伝承館
- YouTubeチャンネル:Akita fes様、go jan様
最終更新:2025/04/22



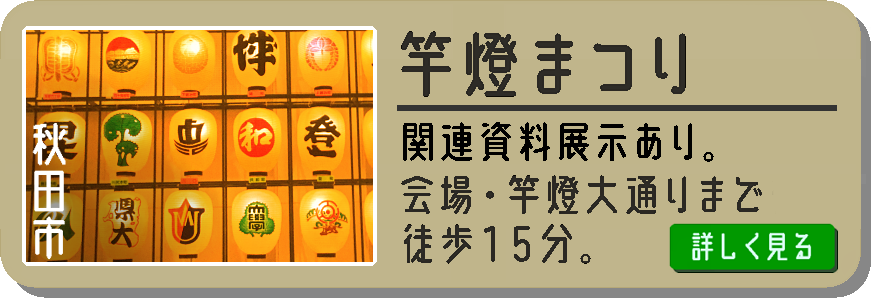
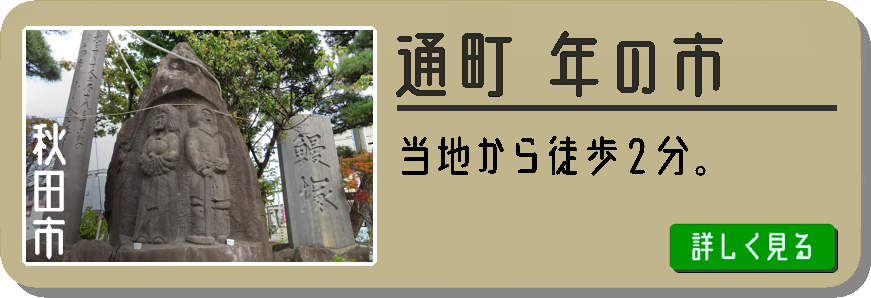
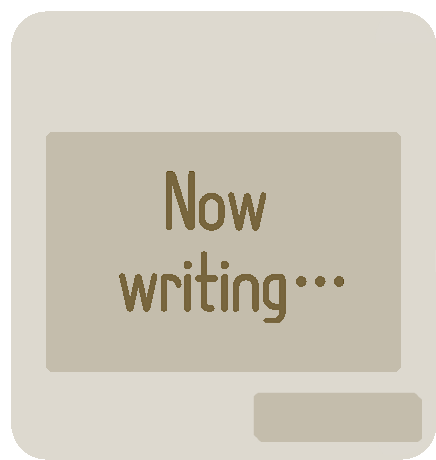


コメントをお書きください